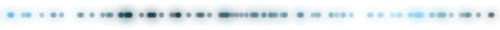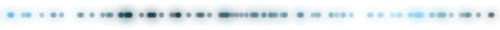


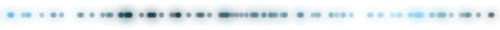
平尾 始(哲学者、武蔵野美大講師・一般教養、基礎デザイン学科)
額田宣彦(画家、武蔵野美大講師・油絵学科)◆作者と作品と見る者の共同体
額田●絵を描きはじめて15・6年になりますが、その間ずっと「自分」をすなおに表出するにはどうしたらいいのかと考え続けてきました。はじめの10年くらいまでは、支持体である「絵画」の形式を相対的に見ていくことで、「相対的に見ている自分」が反映されるのではないかと考えて、今見るとわりあいオーソドックスな抽象を描いていた。でもそれではどうしても「自分」が即物的にしか出てきません。そこで今度は、「自分の主観」を起点にすることを考えはじめました。口で言うのは簡単ですが、われわれはふだん相対的な価値観で生活していますから、好きなように描けばいいということでは「主観的な自分」なんて出てこない。結局「絵画」とは何かという問いに立ち戻ることになりました。そして、「絵画」はすでにあるものだという認識にいたったのです。
「絵画」はイリュージョン(幻影)です。キャンバスの上に抽象的な点を描いてもそれはやはりイリュージョンですし、そもそもキャンバスがあって絵の具で何かを描くという、「絵画」を成立させている形式自体がイリュージョンであるとも言うことができます。それ自体ですでに「小さな宇宙」が完成してしまっている。とすればその「絵画作品」の外にいる作者は、それを包むもうひとつ大きな「宇宙」にいることになる。その「宇宙」を、作品の置かれる場所、作者と作品と見る人の3者ががつくりだす共同体として考えはじめました。そうした「宇宙」をコンセプトに入れてくると、その中にはすでに僕がいますから、もう外に立って相対的に見ることはできません。相対的に見られなければ、仮説としてでも主観的に描かざるを得ない。このシステムは、いわば「絵画」の方から作者に対して「主観的」に描くことを迫るような、最初とはまったく逆の描き方なんです。
平尾●今のお話で、額田さんの絵の変遷がたいへんよくわかりました。以前の作品には、自分と作品を切り離して、対象化して見ようとする苦闘が見えます。でも、そこにもなお、単なる対象ではない「世界」が見えてしまう。それは裏返しに言えば、額田さんは額田さんの見方しかできないということだから、今度は対象を主観化して描こうとする。理性や感性が渾然一体となった「絵画」の形から、付着物をどんどん削ぎ落としていって、ある意味での抽象、あるいは非常にデジタルな手法で描かれる具象になっていく過程がすごく刺激的です。「つくる」ということ、「自分と向かい合う」とはそういうことなんだと、改めてわかりますね。
額田●初期のいわゆる抽象の方が自由に描いているように見えますが、実は今の「ジャングルジム」のシリーズの方が自由に描けています。本当に主観的に描くということは勇気がいる。けれども、そうしないとおもしろくない。このシステムだと、作者である僕自身も全体を見ることができません。じゃあ何をたよりにつくっているのかといえば、作者と作品と見る人の3者が同じ力関係になるようなもの、つまり3者が出会ってはじめて作品が完成するのだから、いわばものの発生する直前を提示できるようにと考えています。最初から見る人と作品の関係が不均衡だと、見る人が作品を通して自己を認識できなくなる。そうしたことを考慮しながら仮説を立てていくという感じです。ですから、描いている過程ではいいか悪いかわからない。無責任に聞こえるかもしれませんが、結果として見る人がいろんな見方で見てくれればいい。そんなふうに作品がつくれる今の状態は、以前に比べてずいぶん解放感があって自由なんです。
平尾●たとえば名画や名作といわれる作品を見る場合には、作品の側にものすごい力、…歴史的な評価の積み重ねや、金銭的な価値、権威のある賞といったもの…があって、こう見なければいけないという圧力が大きくかかるわけです。そうすると、見る側も圧倒的にそれに追従して弱くなってしまう。初期の額田さんの作品も、現代美術の歴史の圧力を見る人にかけてくる感じがある。でも、だんだんそうした付着物を額田さん自身が剥ぎ取っていったことで、すなおに感じがいいとかきれいだと言えるようになる。見る人はそこではじめて一枚の絵として、なんのわだかまりもなく「絵画」と出会うことができる。私たちがものを見るときに、よく「自分の感性」などといいますが、そこには文化の歴史的な積み重ねやまわりの評価、様式性、そういったものがいっぱい付着しています。素直にものを見ているように思っても、実はそこから自由になれてはいない。額田さんの試みは、作者だけじゃなく、見る側も自由になるということなんですね。
◆歴史性の重みとそこからの解放
平尾●今の話を突き詰めていくと、哲学的な「感性」になります。つまり、私たちがそうしたさまざまな付着物を切り捨てていくときに、じゃあ最後まで捨てられないのは何かという問題です。哲学者のカントは、「感性は知覚の能力である」という有名な定義をしています。具体的には時間と空間の直観的な形式のことです。つまり「感性」の一番底にあるのは、私たちが意識をもちながら時間的にものを考えることと、見た瞬間に捉えられる空間や色彩なんですね。ですから「感性」はみんなが持っている。とすれば、ことさら「感性」を問題にする場合には、むしろその付着物である歴史性や、自分と他者が出会ったときに他者に対してどういう態度をとるかといった問題として捉えられていると思います。
時間と空間の直観は取り去れませんが、そこにくっついてくるさまざまな文化的要素はある程度自覚できるし、自覚できれば批判もでき、取り去ることもできるはずです。現代哲学では、先入観なしにものを見る態度のことを「現象学的態度」などといいますが、本当にそれができるかといえば、やはりこれも完全には無理なんですね。日本語を使っていれば必ず日本文化の歴史性がそこにあるし、そもそも言語で考えている以上言語を取り去ることはできない。「感じる」ことと「考える」ことも、はっきり分けることができません。それはきっとどこかで重なりながら、相互に影響しあっている。
たとえば絵を見るときにも、「何の絵だろう」と思ってしまったり、題名に強く影響されてしまう。これを取り去るのはたいへんなことです。現代絵画の試みはそうした様式性を破壊する努力でした。現代美術はこれを推し進めていって、「絵画」や「彫刻」といった形式まで破壊してしまいましたが、現代において「感性」と言うときには、やはりどこまで先入観や自分の生きている社会の歴史性から自由になれるか、といった問いを含んでいるのだと思います。
額田●今おっしゃったいわゆる「絵画」の終焉と言われるようなことは、本当に「絵画」を終らせたかったんでしょうね。「絵画」という形式自体が持つイリュージョンの中ではどうしようもないという閉塞感が、どんどん物質に還元させていった。そうすれば終らせることができる。でもそれは「絵画」の本質からはズレているんです。表現するためには支持体が必要で、それはどこまで行ってもついてまわる。「絵画」はイリュージョンであるというときのイリュージョン自体は、始まりも終わりもなくて、入り口も出口もない。もとからすでにそこにあった。その形式自体を壊していくのは、問題がすでにズレてしまって、もう「絵画」の問題ではないんですね。
平尾●同じことが思想の世界にも言えます。現代はモダン(近代)をなんとか乗り超えようとして、たとえば「ポストモダン」の運動などが起こりました。それは近代思想にある強烈な「自己」という主観との闘いでした。主観があるからこそ人間は「個人」となり「意識」を持つ。今問題になっている「脳死」も、「自己の意識」がないから人の死だということになる。でも人間の主観はそんなに強いものなのか。たとえばナチズムやオウム真理教では、ひとりひとりは個人だと言っているけれども、集団の中で人格をなくしてしまって、個人としては到底容認できない非人道的なことをやってしまった。そうした反省から、本当に「人間」とは何かを考えようということになるはずですよね。ところが「ポストモダン」は、「流行」になってしまって、もうモダンは乗り超えられたのだとか、「主観」や「意味」なんかもはやないんだとか、そんなふうに言い出してしまった。
文学にも絵を描くことにも意味なんかない、そんなものは全部思い込みに過ぎない、思い込みが文化なんだ、というような安易な結論を出す人もいます。みんなもそういう考えには染まりやすい。なぜ染まるかといえば、楽だからです。「意味ない」と言ってしまえばいいわけですから、カントやヘーゲルだって意味ないんだ、今はポストモダンなんだと言っていれば、勉強しなくてもいいわけですよね。
◆創造の「支持体」
額田●僕の友人や学生にも、自分がどうしていいかわからないと言う人がいます。本当は絵が好きで入ってきたのに、たった1・2年で違うことを始めてしまう。いろんな経験を積んで自分を見つけていくならいいですが、やっぱり何をやるにしても支持体は必要なんです。ですから「絵画」や「彫刻」といった形式が、逆に今は有効な気がしています。「絵画」はすでに終ったメディアだと思われがちですが、その「絵画」のイリュージョンをどう扱うかで、見る側の先入観をなくしていくことはできるかもしれない。
平尾●そこで問われるのは、たとえば絵が描きたいのなら、「絵画」のことをどれほど勉強しているかということです。現代絵画の巨匠ジャクソン・ポロックの絵はでたらめに見えますが、じゃあ幼稚園児が同じように絵の具をばらまけばそれが芸術かというと、ぜんぜん違う。やはりこの2千年、3千年におよぶ美術の歴史を踏まえて、それと対決した人が作ってはじめて作品になる。これはどの分野も同じです。歴史性を克服するためには、逆説的ですが、歴史を知らなければいけない。
知らない人が「関係ないよ」と言うのと、知っている人が苦しんで苦しんでそれを乗り超えようとするのはぜんぜん違います。まず歴史や様式をおさらいして、その中で苦しみ、最後に抜け出るところでそれと対決する。そうしたことを経た人は、本当に自由になります。でも自分が何に囚われているのかも知らずに、本当はその中にいるにも関わらず勝手なことをやって、それが自由だと言っている人は、本当は自由ではない。「感性」もまったくそうで、基本的なことを学ばないとそれこそ時間と空間がわかるという「感性」だけになってしまう。そんなものは動物にも植物にもある。人間が表現をするということは、まず過去の積み重ねをどうやって自分のものにするかです。本当に何かをやろうとしている人は、下手でも未熟でも真正面からやる。そこで逃げると小手先のものになっちゃうんですね。
額田●むかしある彫刻家から、「絵画」を捨てられるようになったかと訊かれたことがありました。その時はよくわからなかったんですが、今おっしゃったように、「絵画」をわかったうえで「絵画」を捨てて、自分の「絵画」をそこに持ってくる、そういうことが最近やっとわかってきた。やはりものをつくっていく場合にはいくら言葉でわかっても、作品を通じて実感としてわからないとだめなんですね。それがなかなか時間がかかる。ですから僕が今、「絵画」はイリュージョンであると結論づけて言えるのは、実はかなりたいへんなことなんです。言葉ではあたりまえですが、それは最終的には「絵画」という支持体へと戻っていく確固とした意志の表明なんです。よくドナルド・ジャッドの作品を「彫刻」と「絵画」の中間だといったりしますが、でも僕はそんなものは存在しないと思う。必ず「絵画」か「彫刻」であって、そんな中途半端なものはない。
平尾●私も同感です。どのジャンルにもそうしたあいまいさを許さない奥行きがあるはずです。それが許されているような気がするのは、比較的自由になった素材や道具に助けられているに過ぎないんですね。
とくにコンピュータがそうです。コンピュータを使えば新しいわけではなくて、問題はそれで何をつくるかです。そういう意味では表現というのは、何一つ新しくも古くもならない。ただその時々の私たちのものの見方とともに変っていくだけです。たとえば印象派の時代は物理学が発達した時代で、彼らはみんなパリの物理学校などで屈折光学などを勉強して描いている。そうした新しいものの見方が、それまでの「絵画」とは異なった表現を生んだ。いつの時代にもそういうことがある。
私の本業は哲学や論理学ですが、大学時代以来、四半世紀近くコンピュータを使ってきました。最近は「フラクタル」や「ライフゲーム」の理論を応用したCGを作成して、インターネットにも公開しています。例えば、単純なプログラムから、思いもよらない複雑なイメージが自動的に生成されて、あたかもアラベスクのように展開していきます。部分が独立して偶然的に変化しながらも、全体は統一されている。そうしたシステムは、人工知能や人工生命の研究とも密接につながりながら、生命やわれわれの生活を新しい角度から見る見方を提示していると思います。
そんなこともあって、額田さんの作品がデジタル的になっていくのを興味深く拝見したのですが、私の試みは、単に技術の問題ではなくて、新しいものの見方を、コンピュータでしかできない表現で提示しようということです。そのためにはやはりそれまでのものの見方や、コンピュータというものに対して、真剣に対峙していかないといけない。そうでなければ単なるソフトユーザーに終ってしまう。
◆表現から一直線に離れること、そして戻っていくこと
額田●制作するうえでの「責任」とでもいうようなものですね。「責任」を持とうとするとかなりの不安が伴ってきます。そもそも「自分」を知らなければどう「責任」をとっていいのかもわからない。「責任」を持たなくても暮らしていける日常の雰囲気をそのまま引きずってしまうと、作品の正面に立てずに、だんだんズレていってしまう。で、飽きたら支持体を変えていって、結局まあいいかで終ってしまう。本当は自分の裸を見せてはじめてその人独特の「感性」というか、いい意味でのオリジナリティーが見えてくるのに、そこから逃れようとしてしまう。
平尾●額田さんがずっとテーマにしてきた「すなおに自分を表現する」、あるいは今おっしゃった「裸の自分を見せる」ということがいかに難しいことかということですね。たとえば今、写真を撮っている若者はいっぱいいるんですが、写真はシャッターを押せば写る。とすれば何をどう撮るかが重要ですよね。写真展で作者に訊いてみると、「私のこの時のものの感じ方を撮りました」と言う。でも、ものの感じ方って写るんでしょうか? それは誤解だと思います。悲しい気分で写真を撮っても悲しい写真は写りません。その時の被写体しか写らない。写真家の東松照明さんが、「写真は今しか写らないから、真を写すのではなく写今機だ」とおっしゃっていましたが、まさにそのとおりですね。
額田●作者と作品の距離が近ければ近いほど、見る側の間口はずっと狭くなる。日記を見せているようなものです。でも他人の日記なんておもしろくもない。「写真」を撮るなら最終的に「写真」という支持体に戻ってくるように撮らないとだめだと思います。「絵画」でも、「絵画」からはじまって「絵画」にきちっと戻ってくるようなことを考えないと、誰にでもすぐできてしまうものにしかならない。
平尾●やはり整理して、切って、貼って、さらにそれを練ってから出さないと、その人というものは伝わらない。私の専門の哲学も、「私」というものを一番遠くして、「私」のべったりした日常からどれだけ遠ざかることができるか、逆に言えばどれだけ問題を一般化し普遍化できるかという学問です。例えば、私の「べったりした悲しみ」ではなく、遠くに置いた「私」の悲しみを問うことは、「悲しみ」とはそもそも何かを問うことであり、それはすべての人の「悲しみ」を問うことでもあります。そういう「私」の生きる意味を問うことは、すべての人間の生きる意味ということにつながっていく。ともかくそれは「べったりした日常感覚」から離れなければできないわけで、そこからまた戻ってくることは構わないわけです。
額田●「絵画」にしても「自分」にしても、希望として普遍的なものを目ざしたいという想いがあります。それはやはり「絵画」からどれほど距離を置くことができるかということです。でも離れすぎてしまうと、「絵画」の問題からズレて、白いキャンバスをポンと見せて作品ですということになってしまう。作品との距離をどのようにとっていくかで、結果的にはその作家の感性というか、その人のトーンがじわっと見えてくると思うんです。
平尾●今後、額田さんの絵に出会った時は一目見てわかると思います。なぜなら、「絵画」とは何か、あるいは「自分の絵画」とは何かということが凝縮され、余分なものは蒸留されて、最後に残った「額田さんの作品」がここにあるからです。途中で捨てられたものは、恐らく誰でもやっていたり誰でも感じるようなことで、そうしたものを取り去った果てにここまで来ている。ものを見るとか感じるということには、やはり練習や積み重ねが必要なんですね。
額田●「絵画」独特の空間、つまり絵画的イリュージョンの宇宙は、作者と作品と見る人の3者の共通の基盤ともなり得ます。その「宇宙」に、自分が仮説を立てて描いた絵を置くと、3者の境界がゆれ動いて全体に作用します。そして最終的には一枚の「絵画」に収斂していくような、大きな円環が描かれるような可能性が感じられます。「絵画」から「絵画」へ回帰するその円環が大きければ大きいほど、作品は開かれているし、おもしろい。ただ「絵画」の場合は、それがあくまでもイリュージョンであって、絵の具を使って区切られた矩形とその表面の再生を見せていくという物質的な面はきちんと認識する必要がある。そのうえではじめてその人の「感性」が見えてきて、見る人に何かを喚起させるのではないか。何かを喚起させるということは、相対的にしか見られないものの、そのぎりぎりの狭間をちょっとだけ出たところで、作品との対話が成立するということです。それってとっても大切なことだと思います。
(1999年5月16日・東京にて)
ひらお・はじめ 1954年兵庫県生まれ。'81年、早稲田大学第一文学部卒業、'92年同大学院哲学専攻博士後期課程修了。
ぬかた・のぶひこ 1963年大阪府生まれ。'89年愛知県立芸術大学美術学部油画科卒業。'90年同大学院美術研究科修了。'91年同大学院研修科修了。