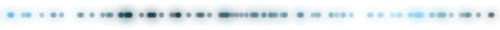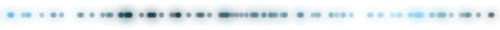


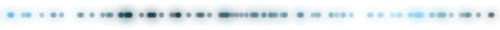
武蔵野美大助教授(対談時) 寺山祐策
武蔵野美大講師 平尾 始
寺山
直感的に言うと、いま出ている興味深いお話、つまり複雑系の話に入っていきますよね。そういうふうに形がおもしろいので、デザイナーとして考えると、それを何かに使おうという感じじゃなくて、そこに秘められた問題をもう一回意味的に取り出す。いまは非常に単純なことにもかかわらず、その単純な原因がものすごく想像もつかないような複雑な現象をもたらすという、ある種のコンピュータの凄味というのを、それが語ってるんだろうなと思うんですね。そこらへんの問題が、複雑系という科学の一つのビジュアライズだと思うんですね。
平尾
ただこれは年代的にいうと、ほんとにこういうことができるようになったのはつい最近ですから、まだまだ研究の余地はあると思いますね。
寺山
ライプニッツとラッセル、ホワイトヘッドというのはつながってるというか、思想的には。
平尾
さっき言った思想にアルファベットみたいなものがあるんじゃないかというところでは、強くつながってますね。ラッセル自身もライプニッツの研究書を出してますしね。ただライプニッツは全体を見るということと、部分を見るということとのつながりを強力に考えていて、小さな部分にも全体が映っているという感じですね。これが曼陀羅と似てると言われるんですけれども。
彼のモナドというのは、一つのモナドはほかのすべてのモナドを映している。ただその映し方は複雑なんで、鏡のように映ってるんじゃなくて、自分の部分の中に全体がもうあるんだと。だから外とのつながりは全然ないのに、自分のモナド内部にある変化を知ると、それが大宇宙の変化であることを知るのだということを言ってますね。これはエコロジーをやってる人には、思い当たるところがあるのかもしれないけれども、具体的に何なのかというのはよくわからない。
それに対してラッセルはそういう考え方はしてないですね。もっと彼は分析的に世の中をとらえようとしてる。ホワイトヘッドの言葉で有名なのは、われわれは意識的に知覚している以上に多くのことを感覚している。つまりぼく達は目で見たり触ったりしてるんだけども、実はわれわれの感覚自体、フィーリング自体はもっと多くのものを取り入れているはずだというものです。これなんかはやはりわれわれが単なる個ではなくて他者とつながっている、あるいは外部とやりとりをしながら流れつつある個であるというようなことを、語ってるんだと思うんです。そういう点では関連はあるでしょう。
ライプニッツは半分は機械論の人なので、彼の哲学を有機体の思想とは言わないでしょうね。有機体の哲学と自ら言っているのはホワイトヘッドが初めのようですね。
寺山
ぼくのイメージでは、ラッセルとホワイトヘッドというのは数学の人だと思っていたし、その後のヴィトゲンシュタインとかのつながり、論理学というんでしょうか、言語学というのか、英米系の思想につながっていくというイメージがすごくあったので、さきの話を聞くと全然違うので非常におもしろかった。
平尾
だいたい英米系の人っていうのは分析的な発想をするんですけれども、その反面思わぬところで発想の転換があることも多いですね。ホワイトヘッドでいうと、数学者なんだけれども、いきなり精神も物質もすべてアクチュアル・エンティティだと、とんでもなく形而上学的なことを言って、これはやはり驚きですよね。精神と物質を一元論でなんとか説明しようとする。
ただホワイトヘッドは、それは自分にはケルトの血が流れているからではないかとか、いろんなことを言ってます。顔もちょっとイギリスっぽくない、頭の大きい、ケルト的と言われるとなるほどというような感じの人ですね。
ライプニッツもそういう意味でいうと、彼はハノーバーの人ですけど、ちょっとドイツ人らしからぬところもありますね。一つは宗教からちょっと自由なところがあります。宗教から自由であるがゆえに、あまりまわりから受け入れられなかったのかもしれませんね。彼はかなり宗教に対して自由な考え方をしていて。あのころはうっかりすると無神論だと言われちゃうわけですけど、たぶんライプニッツも少し自由にものを考えようとしたんでしょう。
彼らの思想を一度翻訳して本を出すというので、『自然哲学の古典家たち』という本が出る出るといって計画ができて、原稿も二年前に出したんですけど、全然できないのがあってね(笑)。(やっと出ました→これです。) その本で、有名な研究者が哲学者の解説をするわけです。すると結論がみんな似通っていて、どの哲学者の考え方もエコロジーに通じるような有機的な思想だと言ってるんです。それがすごくおもしろい。それぞれの研究者が、20世紀末の今、自分が過去の哲学者を研究する意味は何だろうかと考えた時に、おそらく今の世界の中で過去の思想の読み取りをしようとすると、こういう部分に焦点を当てたらいいんだろうと感じていることが、だいたい同じじゃないかと思うんですね。
だから、意外なところにつながりがあって、この人とこの人はこういうところが似ているとか、この人がこんな意外なことを言っているということが、そういう本を作るとわかってきますね。それも現代の、環境問題などに直面した時代のぼく達にとっての「哲学」の受け取り方だと思いますね。
寺山
さっきの構造主義のテキストじゃないけれども、過去のものなんだけれども、テキストとして読めばまた違う読み取りができる。
平尾
そういうことでしょうね。昔ライプニッツやデカルトを読むのだったら、当然キリスト教が下敷きにあるとして読まなければいけなかったでしょうけれど、それから自由に読んでみると違うものが見える。
たとえば、デカルトは宇宙を満たしているのはエーテルで、太陽のまわりを惑星が回っているのはエーテルが流れているからだと言った。これは今では明らかなまちがいだとわかっているわけですが、なんと銀河と銀河が相互作用をしたり、あるいは宇宙誕生後間もない時にどういうふうに銀河団が誕生していったかというところでは、このデカルトの渦動宇宙説に近い動きがあらわれるということが最近言われています。
一度はデカルトの考え方は、エーテルなんていうものを考えていて、まちがいだと言われたのですけれど、デカルト自身は緻密に理論を組み立てていますから、再び別の面から見た時に、これがむしろ正しいんじゃないかと。こういうことがありますね。科学史の上では。
湯川秀樹がアインシュタインのことを、ギリシャの自然学的な発想をした人だと評していますが、これはまったくそのとおりで、アインシュタインの、すべてを一元的に見ていこうとする見方は、今世紀的な発想じゃないんだと思います。つまり、今世紀の発想は分析、分析でやっていこうとしたわけでしょ。でもアインシュタインはすべてを相対論だけで説明しよう。強烈なのは、それが説明できるという信念を持っていたことですね。だから、粒子の位置と運動量は同時に測定できない(不確定性原理)というのは、アインシュタインにとっては我慢できない。だから、彼は晩年は量子力学に背を向けて、一人孤高の道を歩んだと言われています。
これだって、もしかするとアインシュタインの言っていたことで、量子力学の中では通用しないけれども、まだまだ正しいことがあるかもしれないわけです。そういうところがおもしろいところでしょうね。
裏返して言うと、いまぼく達の世界には支配的なイデオロギーみたいなものがないんです。だから、そこでいったい何を現代の、あるいは21世紀の思想にしていくかという時にぼく達は迷っていて、いろんなものを探しているところがあると思うんですね。新しいものはなかなか理解されないから、やはりまず今まであった発想の中から理論を拾い上げようとする。社会学などはそういう学問になっていますからね。
まだ名前の出てきていない過去の思想家がたくさんいると思います。東洋の思想などもそうでしょう。アジアやアフリカの思想の中にも新しい発想に生まれ変わるものがあると思いますね。
ぼく、前にきっかけがあって三浦梅園の本を読んでみたんですけど、梅園が書いていることはほとんどデカルトの思想なんですね。びっくりしました。やはり同じくらいの時代の人だからかな。
寺山
同時代的なんですか。
平尾
同時代人です。同時代に同じ問題をまったく単独で考えていた人がいたんです。三浦梅園は鎖国時代の日本の人ですから、外国の思想を知らない。びっくりしました。言ってることが非常に合理的なんです。
安藤昌益の『自然真営道』もそうですよ。あれは結局散逸しちゃって、ほんとうの形はわかりませんが。『統道真伝』かな、残っている「パンフレット」に当たる部分を見ると、やはりそこに書かれている思想というのはほんとにエコロジーの思想ですね。例えば、すべては陰と陽の動きで起こると言ってます。プラスの方向に動けば春になり、マイナスの方向に動けば冬になる。プラスの方向で生命が生まれ、マイナスの方向で死ぬ。しかしこの世界はプラスとマイナスのリズムのくりかえしである。それですべてを説明していく。だから、これはすごい人だなと思いました。だから、もしかするとそういう過去の思想が発掘されて、これから出てくるかもしれない。一時「タオ自然学」なんていうのがはやりましたね。ああいう思想もその一環でしょうね。
寺山
まあ、デザインとか美術の観点から言うと、同じようなことで言えば本阿弥光悦とか利休とかいった人達をいま客観的に見れば、モダン・デザインのパイオニアでウィリアム・モリスとかと似ていると語られるけれども、本阿弥光悦とか利休がやっていることはもっと先に行っていて、ものは、ものそのもので存在するわけじゃなくて関係性の中でものを考えたり存在しなきゃいけないんだとか、あるいは時間の中で意味が変化するとかね。そういったことをもうすでに生活の中でやってるというのは、デザインという視点からいま見ると圧倒的に優れていたりしますから、そういった面はあるだろうなと思いますね。
さっきの原子の話もそうなんですけれども、これは語弊があるかもしれないけれども、イデオロギーがあまりにも強すぎたり、それに対するいろんな恐怖感が強すぎたということがあったとして、あまりにもリアリティがなさすぎて、アーティストがそのことを真剣に受け止めてないという側面もあるんじゃないかな。
あるいは遠近法だとか、そういったものにあまりにも芸術家自身がしばられていて、それを突き抜けたような、見えないものを感知しなければいけないわけで、なおかつそれを従来とは違う見えで表現しなきゃいけないという、これはすごくアクロバティックなことなわけだから。19世紀からつながって20世紀に発見されたさまざまな世界というのは、もっとほんとはおもしろい、異なった世界であるにもかかわらず、せいぜい20世紀初頭のピカソのキュビズムが断ち切れているぐらいであって、ほんとうの意味での衝撃的な世界に相応するような新しい世界像を結び得ているのだろうかというのが一つありますね。
たぶん芸術をやっていこうと思う人は、20世紀がイデオロギーの時代で済んだ時代とは言えないだろうと思うんですよね。むしろそこで描くべきであったにもかかわらず描けなかったことを、もう一回見ていくことで、何を描くべきか、作るべきかを考える。四次元とか時間とか空間の新しい相対的な関係といった問題を、アーティストはどのように受け止めるのかということがあるだろうなと思う。
ぼくはデザインの世界ですけれども、そのデザインはまさに古い内燃機関である自動車の表面のパッケージを考えたり、それがデザインだというふうに思われている側面が多かったし、それは機能主義だとかモードだとか、せいぜいそんなものでとりあえず作ってきてるわけだから。それからデザインの問題を「見えないアルゴリズム」というか、ものができていく「思考そのもののデザイン」があるみたいな話になると、それこそデザイナーという職能ですら、いまの社会では説明できませんよね。
「デザイン」という言葉自体がだいたい社会の中では、ある形を作ることであるというふうに思われているから、コンピュータが登場してきたことによって、形じゃなくて仕組みも同時にあるんだみたいな言い方が、なかなかデザイナー自身だって気づきにくいし、ましてや社会に対して新しいデザインを浸透させていくというのは、たぶんこれからなんだろうなという感じがする。
平尾
アートの世界では「意味を漂白する」みたいな動きが現代美術にはあるでしょう。どんどんどんどんよけいなものを剥ぎ取っていって、どこまで剥ぎ取れるか。そうするとルチオ・フォンタナの「空間概念」みたいに、「キャンバス切っただけ」みたいになっちゃうわけですけど、それは「どこまで剥ぎ取ってもアートなのか」という問いを発していたわけですよね。
それとまったく逆に、コンピュータというものはもともと無意味なものなんですね。コンピュータが扱うのは、もともとただのデジタル記号ですけれども、その無意味なものからどういうふうにして意味が生まれてくるか。あるいはそれにどう意味づけをするか。そういう問題がコンピュータの中にはあって、さっき言ったようにミニマル化していくようなアートと、コンピュータが作り出す作品がなぜ似てるかというと、意味を漂白していく方向と無意味から意味を作り出していくところが接しているんだと思うんですよ。
そこのところで、コンピュータを使うデザイナーの仕事としては何があるかというと、やはりぼくとしてはおそらく「意味づけ」なんだろうと思います。いままで現代美術の中でいろんな人達が意味ということを考え、そして意味にとらわれ、だからこそ意味を削ってきたと思うんです。しかし、やはりそうじゃなくて、現代の社会の中ではそれこそ無意味なものがただ単に型にはまって製造されているわけですから、それを意味づけすることが不可欠だ。
しかもその意味づけというのは、ちょうど広告が「欲望の生産」という意味で「安っぽい、中身のない話、意味を再生産した」のとはちょっと違う形で、ぼく達の実感であるとか生き方であるとか、そういうものと結びついた意味ですね。そういう意味をどのように、それに付け加えていくか。意味をデッサンしたり、意味をデザインしたり、そういう方向が大切なんだと思うんです。
THE END