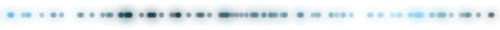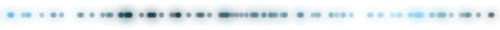


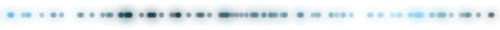
武蔵野美大助教授(対談時) 寺山祐策
武蔵野美大講師 平尾 始平尾
ICCでしたっけ、オペラシティの。あそこの展示物に、一つ形態を選ぶとそれが一〇世代、二〇世代後にどうなるかというのがありましたね。見ました?
最初に豆みたいなものの形態を選ぶ。ボタンを押すと、そいつが別のやつとくっつくとこういう子供ができて、どんどんどんどんやっていくと、最初に選んだ形態によっていろんな子供が生まれてくるのね。たぶんああいうものはそういう発想だと思うんですけど。さっき私が研究してきたと言いましたけど、ホワイトヘッドという人の思想の中にはやはりそういう側面が入っている。まずホワイトヘッドはアクチュアル・エンティティというものを考える。これは難しいんですよ。現実的実質とかいろんな訳があるんですけど、一つの原子的な、アトミックな存在を指す言葉です。そのアクチュアル・エンティティというのが世界をすべて構成しているのですが、ホワイトヘッドによれば、物質も精神もすべてアクチュアル・エンティティの集まったものと考える。ここらへんが形而上学的で難しいんですけどね。
ホワイトヘッドは、そのアクチュアル・エンティティというのは、過去からは因果的な限定を受ける。すなわち原因があって結果としての現在がある。その意味で、過去を自分で持っている。これはプリヘンジョン(prehension)というんです。これも包握なんて訳すんですけど、プリヘンド(prehend)して、過去を全部持っているから今の私がある。それと同時に、今の私には未来の可能性があります。現在に帰結する過去を持ち、開かれた未来に向かうから、現在の私のあり方は、過去を集約して未来に向かう光円錐(ライトコーン)によって図示できるんです。
大事なことは、その過去をぼく達がプリヘンドして、つかんで、未来に向かって生きていく時に、過去に従って未来も決定されているのかというと、ホワイトヘッドは必ずしもそうじゃないと言うんです。一つは、誘因(lure)と言われるもので、未来のほうから私達を引っ張るものがある。
過去がぼく達を限定しているというのは、きわめて客観的な、つまりオブジェクティブな「固い過去」によって、ぼく達は制約され、自由が効かないということです。つまり、過去は変えられない。でも、未来からぼく達に呼びかけるものは、サブジェクティブな、つまり主体的な生き方を促す。ぼく達に「どう生きるか」と問いかけるものが何かあって、たぶんわれわれはそれがあるからこそ未来を信じて生きることができる。
もう一つの要因があって、それは進入=イングレッション(ingression)と呼ばれるのですけれど、「横から進入してくる」ものなんです。例えば、ぼく達はこうやって自分自身のタイムラインの上で、過去を引き受けながら生きているわけですが、こうやって出会いがありますね。突然、横からいろんなものが入ってくるわけです。こうやっていろんな人と話をすることによって、ああそういうことがあったかとか、いままでの自分はまちがいだったと思うと、生き方が変わっちゃいますよね。
このように、もう固まった過去、そしてまだよく知らないけれども、自分を呼んでくれる未来、さらにお邪魔虫で突然入ってくるイングレッション、これらによってアクチュアル・エンティティというのは活動し、現実化していく。これは大変うまいネーミングで、アクチュアルというのが「動いている」ということ、エンティティというのが「本質」という意味ですから、常に活動している本質なんですね。
これはすごい発想だと思うんです。ただ、ホワイトヘッドの哲学というのは難しくて、本を読むだけでも大変なのであまり普及しない。さっきのベルタランフィとか、何人かの著名な学者には影響を与えているのですが、なかなか理解者が増えない一つの原因は難しいからだと思うんですね。
ホワイトヘッドはもともと数学者なので、どうも彼の頭の中には明瞭なイメージがあるようなのですが、問題はやはり言語なんです。言葉で説明するでしょう。そうすると定義に次ぐ定義で、わけがわからなくなってしまう。(現実的実質を始めとする用語はすべて彼の造語です。ジェイムズ・ジョイスみたいですね。)私はホワイトヘッドの言っていることは、ビジュアル化するともっとよくわかって、もっと多くの人に感銘を与えるものだと思っているんです。まあ、それはぼくのテーマの一つということですね。
もしかするとあったかもしれないもの、なかったかもしれないもの、ということを考える時には、いま言った、ぼく達が未来に向かって開かれてるということ、その開かれ方が完全に自由ではなくて、過去に限定されているけれども開かれている。そしてまた希望はあるんだけれども、途中から何が進入してくるかわからない。そういうふうにして考えると、われわれが生きて動いているということがどういうことなのかが、わかる気がするんですよ。
コンピュータのプログラムにもこういう発想があって、色々な名前が付いていますけれど、可能世界プログラミングと呼ばれることもあるんです。どういうことかというと、コンピュータのソフトウェア上で一つ一つ実行されるプログラムを「世界」と考えるわけです。この世界は、横から何かの影響があった時には自分自身を変えて、新しい対応ができるようにしていくんです。しかし、やはり何通りに変わるかということは定義しなければいけないので、何通りかの道を選んでおくわけです。
相手が現れてそこに潜り込んで来ると、この三つの中の右の道を選ぶとか左の道を選ぶとか、ある程度簡単な分岐を決めておくと、先のほうでは非常に複雑な分岐ができてきますよね。そういうプログラミングは実際にエキスパート・システムなどのアイディアとしてもうある。その中でも、枝分かれしていった一つの系列が自分の横の系列と関係が持てるのか、あるいは持てないのか、あるいはもう一度過去を振り返ることができるかできないか、そういうことによっていくつものバリエーションができてきます。
寺山
天文学的に複雑になっていきますね、先のほうになると分岐点が。
平尾
ただ、いくつかのルールさえ決めておけば、結局可能性は天文学的だけれども、プログラム自体は簡単なわけです。それはちょうどカオスの問題なんかに似てますね。簡単なルールから複雑なものができあがる。
それは『美の幾何学』の中で、ほんとうに四次元的なものを発想しようとすると、そこに時間の要素を入れなくちゃいけないと言われています。遡れない時間の要素が入ってくると、短期的には、ある要素に対して結果が局所的にどう出るかはわかる。しかし、長い目で見るともう過去には戻れず、そして遠い未来も予測できないようなシステムがないと、四次元的なシステムを作ることはできないと言っている。それはライフゲームとよく似てるというようなことを言ってるんですね。
ライフゲーム を今日ちょっと持ってきたんです。
いくつかの規則がライフゲームにもあって、これはちょっと規則を変えているんです。最初は六つの個体から出発して、この個体のまわりにセルが八つあるんです。九つのマス目の中心に個体を置くと八つのマス目がある。3、4、2。まわりにあるセルが三個以下だと次の世代で滅亡して、四個以上だと次の世代で生き残って、セルが2個あればその中心に一個の新しいセルが生まれるという規則です。そういう増殖規則を作るわけですね。
そうすると何世代後かに、これがこんなふうになります。こういうふうになることはもちろん予測できません。これがもうちょっと世代がたつとこうなるんです。これはスケールを変えてあります。もうこれは完全にアラベスクでしょう。
寺山
ああ、すごいですね。
平尾
これは簡単な二次元セル・オートマトンというやつなんですが、元がこれですから。二次元のセル・オートマトンの簡単なプログラムから、そういうものができるということです。
寺山
それ、やっちゃってるところがすごいなあ(笑)。ある規則性がありますよね。
平尾
あります。しかも、この場合には対称性がありますが、最初の点の配置を見ただけで、その後の展開に対称性が出てくるのかどうかはわからないです。
寺山
そうみたいですね。
平尾
四つの状態があって、一つは滅亡、もう一つは増殖、もう一つは規則的くりかえし、もう一つはカオスなんです。カオスとは何かというと、予測ができない、くりかえしがあっても、同じくりかえしは二度と起こらないような状態ですね。
−−滅亡というのはなくなっちゃうことですか。
平尾
点の数がゼロになっちゃうんです。ゼロになるかどうかはまったく予測がつきません。なぜかというと、一つ一つのセルがそれぞれに相互作用しながら変化しているので、一つのセルの運命はわかっても、セル全体が相互作用をしながら最終的にどういう関係になるかは、実際に計算してみないとわからないからです。そして、そうした不確定性が永遠に続く状態をカオスというわけです。
ところで、こうやってライフゲームで出てくるセルの形を見ていると、ここにはあるデザインがあることは確かなんですね。それは偶然性から出てきたものなんですが、単なる偶然じゃないんです。いわば計算された偶然です。だから厳密に言うと偶然ではないのですけれども、いままでそれを表現する言葉がなかったわけですね。いまわれわれはそれをカオスと名付けているんです。
ぼくはさっきのホワイトヘッドのアクチュアル・エンティティというのはこういうものに近いんじゃないかと感じています。ルールとしては非常に単純なのですが、時間に沿って動き出すと複雑性があらわれる。たとえば歩き出すセルがあって、それが止まっているセルにぶつかると、止まっているセルもいきなり動き出す。その歩き出すセルを「グライダー」などと呼んでいるんです。そうすると離れたセル同士の間に連絡ができますね。言ってみればさっきのイングレッションみたいな形です。
寺山
外環境みたいなものですね。
平尾
そういうことですね。おもしろいのは、この図などそうですが、表面を持っていることです。つまり内側と外側は区別されていて、その間に表面があるんです。この図形のそばに別の小さな図形を作ってやると、それをまるでアメーバが取り込むみたいな動きをします。だから、ちょうどアメーバがものを食うのにも似てるし、あるいはタンパク質を使ってエイズ・ウィルスがT細胞の上にくっつくのにも似てる。
ぼく達が知ってる生物現象みたいなものをこれでシミュレーションすることもできないではないと思うんですが、ただ、問題はその「法則」が発見されてないことです。
こうしたことができるのはパソコンが速くなったからなんですね。このプログラム自体は1960年代にもうすでにコンウェイという人が考えているわけです。でも、60年代のコンピュータというのは、今のデジタル時計よりも(演算が)ずっと遅いものですから、おそらくこの段階に行くまででも一日かかったと思いますよ。
だからほんとうの意味でのライフゲームの興味深さは、60年代には出てこなかったでしょうね。いまやってみると、もうすぐにでも装飾文様に使えるような図形が出てくるでしょう。しかもこれは一世代ごとに全体がすべて変わってしまうところがポイントです。細部が変わるんではなくて、次の世代になるとすべてが変わっちゃうんです、相互作用によって。
寺山
見た感じが全然……。
平尾
まったく変わってしまいます。だからぐちゃぐちゃした模様ですけれども、止めて見てみると、前の状態と次の状態は何もかも違います。中の複雑さがね。表面から外側に出ている手の数もまったく変わります。
本来、コンピュータというのは、自分がやりたいことを意図して使うものとされているわけですね。でもライフゲームなどでは、「何が起こるかわからないからやってみる」という使い方が出てくるわけです。カオスやフラクタルが見つかったからこそ、そうなったわけですけどね。
こういうふうにいろんなものが出てくるソフトというのは、簡単な構造のものでもたくさんあります。例のフラクタルなんかもそうですね。マンデルブロ集合など。探検していくと神経みたいなものが出てきたりとか。
to be continued