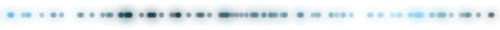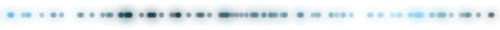


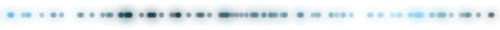
武蔵野美大助教授(対談時) 寺山祐策
武蔵野美大講師 平尾 始寺山
オーガニズムとかシステム論という話が出たので、これもまた私達は知らないので非常に興味深い話だなと思うんですけど、それとちょっと絡むかもしれないので一挙に次に行きますけど、ちょっと出てきた西洋的東洋的という話にこだわるわけではないんですけれども、ぼくがさっき原子とか分子と言った原因の一つに、平尾さんの宿題で本を読んでいて、今度は分子生物学がおもしろいなと思った。私が読んだのは清水博さんの本だった。彼の話が最先端ではないんだろうけど、かなり新しい分子生物学で、さっき平尾先生が触れたような話がいくつか触れられていました。
もう一つ西洋と東洋という話でいくと、その前にチューリング・マシーン、チューリングという人が実験をしますね。それは人工知能として成立するかしないかみたいな話。これもそこに存在しているかしていないかを確かめる一つの方法であったりするから、さっきの話とちょっと絡むと思うんですけど、チューリングの話はたぶん後で出てくると思うので、置いておきます。
同じように一九四五年、つまりコンピュータができた前後のころにノーバート・ウィーナーとかグレゴリー・ベイトソンとか、そこらへんの何人か非常に興味深い人達がいるわけですけれども、その中でフィードバックというシステム、あるいはサイバネティックスという考え方。これは生態学の考え方なのかもしれない、これも線型と非線型と絡むのかもしれませんけれども、いま現在あるのは過去に自分が何かをした結果であるという。
いま現在があるのは過去の原因にさかのぼっていて、それは永遠に続いていくという発想自体が西洋合理主義の一つの考え方の根本にあるんだけれども、同時にそれは因果応報とか、東洋の輪廻といった時間のとらえ方の発想ともどこか似てますよね。むりやり西洋と東洋を結びつける必要もないと思うんだけれども、分子生物学と同時に、コンピュータが出た前後にそういう思想が出た、何かつながりがあるのかどうか。
平尾
やはりコンピュータが生まれてくる動機の一つは戦争なわけです。これはもういろんな人工知能の本に紹介されているとおり、暗号解読をする、そしてもう一つは弾道計算をする。ここらへんの必要性からコンピュータのようなものを作ろうということが出てくるわけです。その時に一方では、数学的あるいは工学的な面からコンピュータが構想されるわけです。実用的なものは数学的・工学的な面からできた。
ただ問題はコンピュータが人工知能のように考えられてくるというのは、明らかにコンピュータがフィードバックができる機械であるという性格を持っているからですね。こっちのほうは必ずしも工学的・数学的オンリーの発想ではなくて、むしろ生物の体をどういうふうにとらえるかという方向から出てきたという点では、現代の工業生産でアイディアと作るということが別々に出てくるのとよく似てるんです。
ウィーナーとかベイトソンとかベルタランフィもそうなんですけれども、そういう人達の発想の中にあったのはそれまでの生理学的な、言ってみれば生物を(人間もそうですが)刺激と反応の関係で(神経細胞を刺激するとその結果運動などの反応が出てくる)定義するんじゃなくて、生きたままどうとらえるか、生きるということの変化をどうとらえるかということの興味だと思うんですね。
それは二〇世紀の前半に(特にそれは戦争の時代とナチズムの時代を含みますが)、生き物とか人間とかを機械的に分析し、要素に還元していく方向に対する反省が出てきたことが根底にはあると思うんです。ただし大事なことはそこのところで、ウィーナーがやったことがそうですが、情報という考え方が入ってきます。ウィーナーの大きな業績の一つは情報処理の発想だと思うんです。情報というものをウィーナーはかなり広くとらえていて、情報というのは生体で言うと「外部とやりとりされるすべて」が情報である。ものを食って排泄物を出すのも情報交換だというわけです。
もう一つは情報というアイディアに加えて、数学的発想が最初から入っている。どうやってそれを数学的に表現するかというアイディアがあるということです。ここで実は新しい数学の必要性が出てくると思うんですね。これはよく言われることなんですけど、数学というのが19世紀の半ばぐらいからどんどんほかの学問と離れていくんです。数学者って、数学は自由だというスローガンのもとに、役に立たなくてもいいことをやる(笑)。興味のあることをどんどんやっていくというふうになっちゃうんですね。
するとどうなるかというと、数学の中にはいろんなアイディアがあるのに、それが実用の中では生かされなくなっちゃうんです。これも有名な話で、アインシュタインが非常に数学的問題で苦労したという。四次元を扱う時には要素が四つあるわけですが、その四元の連立方程式、しかもそれが時空間の中のもののふるまいを記述する時に、時々刻々変化していきますね。その表現と解法に困っていた時に、友人のグラスマンが、それは行列を使えばいいんだと、当時最新だった行列のアイディアを教えたという話があります。
同じように、今世紀もそうなんだけど、普通実用的に数学を使っている人というのは、その中では数学的発見はしませんから、いままであるものしか使わない。言ってみれば職人が同じ道具を使ってものを作るのと同じですね。ところが戦後の、特にコンピュータが生まれてくる過程の研究のしかたというのは、新しい数学的な武器を知っている人達が新たに生物を理解するとか、あるいは自然を理解するという現場に出てきたわけです。
そうするといままで人々が基礎論の分野や論理学の分野ではそういうことがやれたかもしれないけど、自分達には関係ないと思っていたようなアイディアが次々に出てくるわけです。それが非線型となったわけですね。非線型なんていうのは、実際に実用になるとは思ってなかったと思うんです、多くの人は。しかしながら非線型で説明しないと説明できないような法則性が生体の中にあるらしい。特にそれは生体というものが刺激と反応ではなくて、全体性として成り立っているというアイディアが出てきたからこそだと思うんですけど、それが最初に実用化されたのが情報の理論なんですね。
情報の流れということを考えていく時に、外から情報を受け取って、処理して記憶してアウトプットする。最初はウィーナーの考え方というのは一種数学的なアイディアとして、非常に難しいものとして考えられていたんだけど、しかし技術のほうがそれに追いついてきて、それを実際にコンピュータの演算装置と処理装置、入力出力の機器の中で実現できるようになると、具体的な実用的なアイディアであることがわかってきますよね。そういう動きが、コンピュータが誕生するところにはあったと思うんです。
そこでも東洋的なアイディアを、ウィーナー自身は持っていたかもしれません。しかしそれが実現されていく過程では、まだそれは出てこないですよね。それはくりかえしくりかえし、いろんな人のアイディアの中に出てきてはいても、なかなか全体を有機的に構成するというアイディアは難しい。でも、たぶんこれからはそうなると思いますね。さっきのチューリングの話もやはりそうなんですけど、その時に出てくるアイディアが、偶然、名前は同じですけど、機能主義というアイディアなんです。
寺山
チューリングの語った?
平尾
心の哲学、フィロソフィ・オブ・マインドというのがあるんですけど、それで言うところの機能主義ですね。
寺山
それはチューリングの著書ですか。
平尾
いや、アメリカの大学にはどこでもフィロソフィ・オブ・マインドという講座があるんです。こういう分野があるんです。しかし日本の大学にはないんです。不思議でしょう。それは日本の哲学が明治維新の頃のままだから。日本で哲学というとドイツ観念論なんですね。まだ大学院ではヘーゲルなどの研究室が多いでしょ。しかしアメリカではフィロソフィ・オブ・マインドが主流の一つです。例えばこれはMITで作っているテキストなんですけど、アリストテレスから現代のチョムスキーの理論やパトナムの理論、あるいはコンピュータ科学者の理論まで全部、この本の中にいくつかのテーマにしたがって整理されているんです。
このフィロソフィ・オブ・マインドの理論の中で機能主義、ファンクショナリズムという考え方が出てきて、それは何かというと、19世紀ぐらいまでの刺激と反応というのはメカニズムといいます。つまり機械論です。これは基本的には刺激と反応の関係があって、法則的であって、観察してわかる。だから、「中身」をよく見ればちょうどテコの原理が働くように、歯車が働くように働いている。ところが機能主義というのはまったくそれと違っていて、「外部からの観察」によって物事を見ていく。
それはどういうことかというと、チューリング・テストというやつがそうなんですが、箱の中に人間を入れて、こっちから質問カードを出して答えのカードを書かせる。人間が入ってると「こんにちは」と言った時に「こんにちは」と返す。チューリングがやったのは男と女という実験です。男か女かわからない人が入っていて、外の人が男か女か当てることができるか。おそらくやってみると当てることはできないだろう。すなわち、女が男の振りをしたり、男が女の振りをしたり、そういうことを言語という情報のやりとりだけで完璧にうまくできたとしたら、私達はたぶん、中に入っているのが男か女かわからない。それは原理的にわからないわけです。
もう一歩仮説を進めると、もし中に機械が入っていて、いま言ったようなことをシミュレーションできるとしたら、中に入っているのが機械か人間かわかるだろうか。結局チューリングの考え方は、それは「原理的に」わからない。つまり、機能主義の考え方に立つかぎり、ある機械が人間と同じことができれば、それは人間と同じである。つまり「人間と同じ」の意味が変わったわけですね。それまでは人間と同じものを作るというと、フランケンシュタインみたいに、部品が同じでなければいけない。同じ部品で作るというのが古典的なアイディアだったわけです。
しかしコンピュータの領域では、機能主義的な考え方が入ってきてから、同じものを作るという考え方がまったく変わった。意味が変わってしまった。どういうことかというと、同じことができれば同じなんだと。だから、材料は違うんですけれども、コンピュータもまた一種の人間と言えるだろう。
これはウィーナーの場合だったら、ウィーナーがある方程式を書くことによって、人間がものを見てからそれに手を伸ばすまでの過程を記述するとか、あるいは人間のある関節の部分の設計図を描くことによって、その関節がこう働くということを表現する。そういうふうになるわけですね。
その時に大事なのは、「働」きということがそこでは中心に据えられていて、そもそもメカニズムが同じでなくてはいけないということではないということですね。アシモフとかカレル・チャペックとか、いろんな人のロボットに関する考察があるのですが、やはりロボットを実用化する時に一番大事なことは、人間型にこだわらないということ。つまり最初はロボットというのはどんなボックス型でもかわまない。でも、もしもそれが非常に機能的に高められていくと最後には人間型になっていくだろう。それをビジュアル化したのが手塚治虫ですけど。そういうふうなことを実際に考えるようになったわけですね。
そこで大事なアイディアの一つというのは、いままでとは違うような数学、それはやはりデジタルという考え方が出てきて、そこで初めて先ほど述べたブール代数が実用的になってくるわけです。つまり、yes、no、and、orというものが代数的に示せて、しかもそれは計算できて、そしてすべての記号を数学の中で扱えるように変換できる。さっき寺山先生は変換という言葉をお使いになったんですけど、この変換というのが実は戦後の、特にコンピュータ技術を支える大きな問題になってくるんですね。
ウィーナーというのは、いってみればアナログ的に生きている生物をデジタル的に、数学的に記述しようとした人だと言えるでしょうね。コンピュータというのも同じで、デジタル的な機械によってアナログ的な機械を代用しようとしたわけです。あるいはアナログ的なものをコントロールしようと。このような変換が次のエポック・メーキングなできごとだったと言えると思うんです。
さっきの見えないものを見えるようにするというのも一つの変換ですけど、その変換の中にもう一つの変換があって、アナログ的なものをデジタル的にする変換、あるいはその逆。これがすごく大きいと思います。これによってぼく達はいままで計算できなかったものを計算できるようになり、いままでまねできなかったものをまねできるようになるというところに来たわけですね。
編集部
−−変換する時に、スタティックなシステムみたいなものを作る場を設定しないと変換できないということがあると思うんですけど、その時に、先ほどの「観察する時に見るために光を発射して」という時にずれるわけですね。そういうものって設定できるのかどうかと思うんですけど。
平尾
つまり対象を変換できるものとしてとらえる時にずれができるという?
編集部
−−スタティックなシステムを設定することが可能なのだろうか。つまり変換する時にはあるフィルターを通さなければ変換できない。そのフィルターそのものがそもそも揺らいでいると思うんです。
平尾
そのフィルターはなんで揺らいでいるの?
編集部
−−つまり観察する時に……。
平尾
フィルターというのが観察者の持っているフィルターということ?
編集部
−−主体を超えたところで、外部に設定するわけですよね、何か対象の外側に。
平尾
科学ではね。
編集部
−−その時に、変換するための原理というか……。
平尾
具体的に最も基本的なAD変換、アナログ・デジタル変換のことを考えると、やはりAD変換の根本というのは、変化する量をデジタルな数字に写し換えるということだから、たとえばボリュームだったら10度の回転角というのを何分割して数値にするかということになりますね。同じように画像だったら、変化する量としての形をマス目に区切って、座標の上にXとYでドットを打っていくことになりますね。そこからこぼれるものはあるわけです。
音響機器などのボリュームはいま全部デジタル・ボリュームになっているわけでしょう。でも、回転ボリュームでは原理的には無限に段階があるはずだ。しかし、もしもそれをデジタル化しようとすると、段階的なデジタル処理ではマイナス60デシベルとマイナス55デシベルの間には5デシベルの飛躍がある。ただ、ぼく達の耳で聞いても、それはよくわかんないけどね。しかしそこには必ず飛ぶところがある。だから、アナログのレコードの音とデジタルのCDの音はやはりどこか違うと、クラシックファンは言いますよね。
そういうずれは確かにありますよね。変換するというと、どうしてもそれが出てくるわけです。ただ問題なのは、そのずれをある程度小さくすると、人間の知覚の限界で、ずれには見えなくなっちゃう。そうすると今度は知覚の問題が変わってきて、つまり、どこまでそのずれを大きくしても人間にはわからないか、ということになります。情報のやりとりの時にはそれは大事ですよね。インターネットで画像を送る時に、どれだけ粗くしても大丈夫か。デジタルカメラがそうですけど、CDも「サンプリング」はそういうことでしょう。
そういう問題が出てきて、変換ということが入ってくると、変換する前とした後のものは同じかという同一性の問題が出てくるんですよ。これはぼくがいま関心を持っていることの一つで、同一であるとはどういうことか。これはアイデンティティの議論として有名なんですけど、大雑把に言っちゃうと、例えば、脳の記憶を全部電子頭脳に置き換えるとこの二つのものは同じなのか。
ぼくが子供のころはこういうことを言ってるとSFだと言ってたわけ。ぼく達が子供のころに読んだマンガはみんなこれなんですよ。『エイトマン』がそうだし。あれは東八郎(芸人ではない)という刑事が死んで、その記憶を全部ロボットに写し換えるんです。数年前、夜中にやっていた『ブラックアウト』ってドラマもそうだったし。(山本未来が出ていた。)あるいは『トータル・リコール』もそうでしょう。その時に問題になったのは同一性ですね。これはいま哲学者が研究してる。
だから同一性の問題は30年前にはマンガだったんだけど、いまは哲学の問題なんですね。大きく言えばそういう問題だし、もっと小さくたとえば芸術の問題として考えるとどうなるか。ぼくはこの企画が出てきてから、ちょっといくつかそういうことをやってみようと思って、たとえばモンドリアンの作品をソフトウェアで作るとどうなるかというのがこれなんです。ソフトウェアを工夫すると、数値を入力することによってそれぞれの色面の配置を変えることができます。例えばこうなるわけです。
編集部
−−「インター・コミュニケーション」の0号か1号かに出てませんでしたか。
平尾
そうですか?こうやった時に、どれが本物のモンドリアンかという問題が出てくる。もしもモンドリアンが幾何学的な発想で、彼は画家だから「デザイン」とは言わないけど、幾何学的な発想でこのような構成をしたのなら、モンドリアンは作品を描いてないだけで、もしかするとソフトウェアの作ったものもモンドリアンの作品であり得るわけですよね。
そうした時にぼくが思うのは、これはフェイクなのかという問題です。もしもコンピュータが勝手にデザインするとしますね。そのコンピュータのデザインがオリジナルのものだとしたら、さっきの最初の「モンドリアン(風の作品)」も次の「モンドリアン」も、その次の「モンドリアン」も全部、コンピュータとしてはオリジナルとして区別なく作っているわけです。おそらく一般の人が見せられれば、どの作品も全部同じ作家の作品だと思うでしょう。
アナログをデジタルにするというのはこういうことで、デジタル化すると、アナログの時には考えられなかったようなバリエーションがそこから出てくる可能性もある。つまり、これらの絵をもしも油彩で描いてみろと言われると手間がかかります。でもデジタルの世界では、キーボードに数字をいくつか打ち込むだけでバリエーションはいくらでも作れるし、その元になったプログラムもいくらでも作れる。
たとえばいまのプログラムは簡単なBasic(ベーシック)言語で作られていて、これをぼくは「だれでもモンドリアン」と名付けているんですけど(笑)、たったこれだけの行数でいまのソフトができちゃうわけです。しかも初歩的なベーシック言語で。たとえばモンドリアンの作品の写真を撮ってそれを勝手にぼくがウェブ・ページに載せると、それはたぶん著作権に触れると思うんです。でもコンピュータ・プログラムを作ってこれを載せた時に、それは著作権違反なのかという問題がある。
変換によっていままでオリジナルだったものがそうではなくなったり、変換によっていままでフェイクだと言われていたものが実は本物と同じになったりするんじゃないか。これはミニマル・アートの作品にも言えることで、たとえばこれはブリジット・ライリーの『礁』という作品を、コンピュータでぼくがシミュレートして作ったものなんですけど、元はこれ(今は亡きセゾン美術館のパンフ)です。ぼくのほうが色がきれいなんですけど。(笑)数学ソフトの「マセマティカ」(Mathematica)で作るとこういうものができる。元の絵はだれもが認める作品です。じゃあ、これは作品じゃないかという問題ですよね。やはりこの絵もそれなりにプリントアウトして飾ったら、「作品」にはなると思うんですよ。
だから特にポップアートやミニマルアートは、バザルリなんかもそうだけど、ほとんどコンピュータで簡単にシミュレーションができてしまう。そういう時にオリジナルはどこにあって、何がフェイクなのか。ぼくは基本的には、もうこうなってしまうとオリジナルとフェイクの違いはないと思う。これは情報社会論の基本で、デジタル情報には「元」も「複製」もないということです。情報はすべて相対化され、均質化されてしまって、オリジナル情報はなくなってしまう。それがここには出てくると思うんです。
ついでにもう一つ、さっきアヴァンギャルドの話が出たんですけど、昔のアヴァンギャルドがもうアヴァンギャルドじゃなくなってしまう一つの例です。これはハンス・リヒターが1921年に作った『リズム1921』という実験作品の一部のシミュレーションです。『映画の理論』(岩崎昶・岩波新書・絶版)に紹介されていますが、見たことありますか。
編集部
−−ないです。
平尾
ぼく、昔フィルム・センターで一回見たことがあるんです。たぶんそれも火事で燃えちゃったと思う。あの火事の前です、学生時代に。
これなんかは1920年代には最も新しい映画という手段を使って、しかも映画というのは活動写真だったわけですね。まだその活動写真に毛が生えたというころに、もうすでにそれを表現の道具として使っていた作家がいたわけですね。ただ、この人達のやり方は当時はおそらく全然理解されなかったでしょうね。こんなもの見て何がおもしろいんだと思ったと思います。でも、私はいま作ったのをマッキントッシュのデスクトップに張りつけて実際にながめてますけど、張りつけておくと気持ちいいんですよね。いつまでもボーッと見てると、デスクトップ・アクセサリーとしてすごく気持ちよかったりします。
かつては動かなかったものが動くようになる。そしてかつてはこれを映画で撮るのはけっこう大変だったと思うんですけれども、しかしいまコンピュータではそれが簡単にソフトウェアで実現できる。しかも四角を描いたり丸を描いたりするのはコンピュータの得意技です。そうするとかつてアヴァンギャルドだったものが、いまぼく達の視覚の中ではデスクトップ・アクセサリーぐらいになっちゃう。
そうすると結局そこで起こっていることは、やはりこれもなにかしら変換の一つだと思うんですね。つまりアナログ的なものをデジタル的に変換したために、それはぼく達の知覚が広がって、知覚がより新しい能力を獲得したということだと思うんですけれども、昔の人が不思議だったことや昔の人が意表を突かれたものがだんだん日常化してくる。それのいい面というのは、それらをぼく達が楽しめることになった。すなわち純粋なデザインであるとか、絶対的作品であるとか、そういうもの自体をわれわれが受け止めるだけの心の広さみたいなもの、スケールができてきたということだと思うんですよ。
コンピュータが生み出したものはいろいろあるんだけれども、原理的にはさっき言ったみたいに変換ということが大きい。その変換というのがいま一番新しい、つまり人々に受け入れられやすい知覚や感性の面、世界をどう見るかという受け取り方の面からだんだん変わっていってるんじゃないか。
いままでだと抽象的なものはわけわかんないと言われて片づけられていたものが、だんだん受け入れられるものになってきているんじゃないかという気もするんです。それもデジタル化ということのプラスの面、明るい面ではないかと思うんですよ。ただ、こうやってデジタル化ということがデザインの世界、美術の世界に影響を与え得るということは、実際にやってみせるからできるんですよね。できるんだけど、じゃあどれぐらいの美術学生がそういうことに対して、なるほど、おもしろいなと興味を持ってくれるかという問題ですね。
というのは、彼らのまわりにはもうよくできたソフトウェア、道具として完成されたソフトウェア、「イラストレーター」や「ディレクター」や「フォトショップ」がそうだと思うんですけど、そういうものが溢れていて、ちょうどテレビの中身を知らなくてもテレビを見られるように、使う方から見るとこんなのつまんないなというふうに思いがちでしょ。そういう点で大衆化された物事の受け取り方になっちゃうと思うんです。
ぼくは昔ラジオ少年で、ラジオを自分で作って最初に放送が聞こえた時にものすごくうれしかった。そういうふうな体験を普通の人がどこかでする機会があれば、これは全然世の中の見方が変わるんじゃないかと思います。それはコンピュータも同じで。この『美の幾何学』という本の中で伏見康治さんが、いまは体を使って何かをやるということがなくなって、線を引いて図形を作って補助線を引いて証明する、それがなくなって頭でっかちになっちゃって、手応えのない数学だ。頭は使うけど、手応えがない、数字だけ書いてもしょうがないと言ってるんだけど、それとよく似た問題なんですね。
つまり手応えのあるようなコンピュータの使い方ってあるんですね。それは非常に簡単なプログラム言語を使うとか、一つ一つ意味を理解しながら行を、プログラムを書いてみるとか。その結果何が動いたり走ったりするかを自分で確かめる。そしてもう一度それをもとにしながら、次の試みをやる。これはまさしくウィーナーの言っているフィードバックです。そういうことをやっていくことによって、たぶんデジタル的なものがいままでぼく達が過ごしてきたアナログ的な、ものを作るという感覚の中に再び戻って行くと思います。
コンピュータの画面を見ながら、ここの数字をちょっと変えてみようと思うんだよなと言ってる人は、ちょうどノミを持ってここの角を削るのがうまくできないんだよなと思ってる人と同じ感じ方をしてるんだと思うんですよ。それをなんとか獲得していけるようなデジタル環境になっていかないと、さっきの再生産の原理が現代を支配しているように、コンピュータのプログラム自体もつまらないプログラムの再生産になる。そしてまたそれを見る人達の去勢されたような感性の再生産になっちゃうと思うんです。
そこにもう一つ何か驚きを打ち込む必要があると思うんですね。それはできると思うんだけど、ただ、いま言ったように根本的なところでコンピュータとは何かというのは、まだみんなわかってない。それがわかる時が来るのかどうか、もう一つは少しでもそこに近づくためには教育、あるいはデザインの場でそういうふうなアイディアをどこかで入れていかないといけないんじゃないか。
ちょっと話がそっちに向いて来たので、ぼくが考えてきたことをお話ししたんですけど。
寺山
いまのモンドリアンのある作品を取り出してくる時には、これはモンドリアンがベースになる面をどういう比率で設定したかとか、彼が空間を分割する時にどういう比率で分割したかというふうに、彼がやった作業をもう一回言語化するというか、分析し直さなければプログラムは書けませんよね。ですから、プログラムを書くことによってモンドリアンを追体験するわけですよね。追体験することによってモンドリアンが思考したことをある面で共有することはできるかもしれない。それからモンドリアンは確かに作ってないかもしれないけれども、作ったかもしれないというものも同時にシミュレートする、共有することができる。
そういった意味ではモンドリアンの作品をそのまま模写するというのもこれもまたおもしろいことなんだけれども、同時に模写では見えないものが見えてくるだろうと思うんですね。非常に興味深いんだけれども、逆に言うと当然それはモンドリアンを理解したことにはならないというのは明らかになりますね。つまりそれはモンドリアンの全体、彼はそれだけではない方法でたくさん描いたわけだから。逆に言うとコンピュータが明らかにしたことによって明らかになったものという意味では、非常におもしろいと思いますね。
ハーバート・サイモンの、ぼくがたまたま読んだことのある『システムの科学』、彼はいわゆるエキスパート・システムといったもの、思考のプロセスをもう一回たどり直すことによって、コンピュータの場合には当然記述しなければならないから、それを共通言語に置き換えることが可能だということによって、それぞれ全然別の、音楽をやる人は音楽の言語をしゃべっているし、絵を描く人間は絵を描く言語をしゃべっているんだけれども、それらがコンピュータによって一回変換することによって言語を共有することができると言う。
当然音楽家と美術家はそれまでだったら共通の言語がないから語り合えないものが、コンピュータを介して共通の言語を持ち合うことができるというふうな話をいま思い出したんですけども、そういう意味においてはすごく重要だし、おもしろいことですね。
その時にさっき出てきたようなある種の限界もあると思うんだけれども、その限界というのは、フィードバックは必ずその原因を過去にたどりますよね。これはある閉じられたシステムの中だったらば、すぐ工業製品化されたようにクーラーなんかである温度に設定すれば、温度が上がればスイッチが入るし、下がれば切れるみたいな、フィードバック・システムは閉じられた環境の中では何の問題もなく機能するわけです。
でも、たとえばモンドリアンがかつて描いたものを再生産することはできたとしても、そういったものをいくつか集めることによってモンドリアンが描かなかったかもしれないけれども、描いたかもしれないもの、つまりあり得ないものにもう一発ジャンプしようと思った時には、清水さんが言ってたんですけども、フィードバックとフィードフォワードという、次にこうありたいためにはどうしたらいいかというジャンプ。人間は現実的にはジャンプしているわけですね。
これはすごく難しいんだけれども、フィードフォワードとフィードバックがかみ合わさったようなホロニック・ループという言葉を使ってました。それが1950年代・60年代のコンピュータ科学とかシステム論だとまだフィードバックで、分断された瞬間瞬間じゃなくて時間的な全体の中で行われていることがつかめるようになった。ある種のシステムだったらいいけれども、それだけでは済まなくなる。つまり変化する外環境に対してどう対応していくか。
平尾
しかもやりとりをしながらね。
寺山
そこらへんが、もう一つ何かあるのかなとも思ったんですけどね。それは造形の問題には簡単に具体例としてはなかなか出ないんでしょうけどね。
to be continued