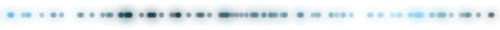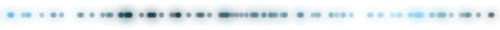


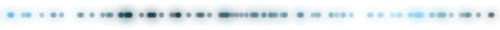
武蔵野美大助教授(対談時) 寺山祐策
武蔵野美大講師 平尾 始寺山
ちょっとランダムに平尾先生に質問していきますけれども、やはり同時代的にというか、ほぼ前後してソシュールの言語学というのがありましたね。これもその後構造主義という考え方が出てきましたね。非常に興味深い考え方で、二〇世紀的なものだと思うんですけども、ソシュールの言語学でラングとパロールの説明がある。これはラングをパロールが規定するわけだけれども、パロール自体はラングがあることによってしか成立しない。これもある種の関係性とすれば、非常に相対的な関係なんですよね。
人間の話す言葉というもの、言葉自体がそういう相対的なものであるというふうに言ったという点においては、分野は違うというべきなのか、ある意味ではすごく同時代的に出てきたものの考え方じゃないかと思うんですね。平尾
ソシュールも今回のテーマで言うと一つの大きな流れの中に位置づけられる。それは構造主義もそうなんですけど、見えないものを見えるようにするという、非常に大きな思想なんですね。つまり構造主義自体が、見えない構造を見えるようにするという考え方なんですよ。だからソシュールにしろ、レヴィ・ストロースにしろ、構造主義の祖と言われる人達の思想の中にはそれがある。
見えない構造を見えるようにするということと、もう一つは、さっき言われた相対性の問題ですね。ソシュールの理論の中では、通時的=歴史的な発想と、共時的=空間的な発想とが、二つの大きな枠組みなんです。
ソシュールが通時性、時間性で言っていることは何かというと、時間的相対性ですね。いまのぼく達が持っている言語と、今から100年前の言語を比べた場合に、言語には「変化の法則」があって変化します。しかしながら大事なことはどちらも同じ日本語ということですよね。いまぼく達はこれが日本語だと言っているけれども、そうじゃないんじゃないか。100年前の日本語も日本語だし、1000年前の日本語も日本語だ。それらを同じように扱って(比較することで)言語研究ができるというのが、ソシュールの非常に大きな発見の一つですね。
そこからもっといろんなことが出てくるのは、それは同時に空間性にもつながっていて、共時性、ぼく達が同時代的にいろんな言語を使っていることをどう考えるかというと、小さな側面でいうと方言の問題がある。ぼく達は東京中心の、(これこそが日本が明治維新以後の近代主義の中で持っている最も大きな要素で、しかもいま克服できていない要素ですけど)、中央集権的な、東京中心の発想をしている。この東京中心の発想をすると、方言というのはダサクて、普遍性がなくて使いづらくて、ということになる。
ところがよく考えてみると、方言というのはさかのぼっていけば50年前の日本語、100年前の日本語、1000年前の日本語で、柳田国雄が『蝸牛考』で書いてますけど、京都の言葉が円環状に伝播していま地方に残っているわけです。青森の人に聞くと、おばあちゃんなんかは夜中に目がさめることを「驚く」といまでも言ってるんですね。これは古典の言葉です。青森ではそれをまだ使っている年配の人がいるわけです。
ぼくはしばらく名古屋に住んだことがあるんですけど、名古屋では「そうでなも」のように、語尾に「なも」という言葉を付けたりする。この「なも」というのは奈良時代の終助詞です。そういう意味では方言の中に時間性がちゃんと眠っているわけで、もしも昔の日本語も日本語だとしたら、方言も日本語だということになりますね。
ソシュールの時代、言語学の流れの中で出てきた大きな理論の一つは、言語には祖語、先祖の言葉があるんじゃないかという発想です。これはヨーロッパの言語、インド・ヨーロッパ語族、ギリシャ語とラテン語とサンスクリット語などはみんな兄弟ですから、そうすると、結局ぼく達がいま「外国語」と言っているものは、ただ単に祖語が変化しただけのものになりますね。そうすると、「英語中心主義」とか「ラテン語中心主義」とか、そういうものが崩れていく。つまりどこの言葉も先祖は同じで、その子供達にすぎないということ。こういう強力な相対主義というのがソシュールの思想にはありますね。
もう一つはさっき言われたパロールとラングの問題で、実はパロールとラングの問題というのはコンピュータにも通用するところがあると思うんです。ぼく達は社会の中で育つからこそ言語を習得し、言語を使わなければいけないわけですよね。しかし同時に言語を使うということは、無限に近い話題があるわけで、常に創造的に発話しなきゃいけないということがある。その創造性の部分がパロール、個人の言葉によって担われる。そして社会的な言語がラングとして考えられている。
コンピュータの言語で人間の思想が表現できるかどうかを考えると、結局コンピュータの言語は数学の公式のように作った言葉ですから、ラングはあるんですけど、問題はそこで「個人の言語」を作れるかどうかですね。つまり個人が勝手に書いた文法をコンピュータがいいように解釈してくれるか。いいように解釈するというのは、これは「揺れ」であって「本当はこうだ」という意味じゃないですよ。「本当はこうだ」というのは、今のパソコンのファジー辞書はそう解釈してくれますね。まちがえてトオキョオと書いても東京と変換するようなものです。そうじゃなくて、東京をトオキョオと書いてしまった人にはそれなりの理由があって、これは特別な言葉だと認められるか。
もしもコンピュータの人工言語が一人前の言語としての性格を獲得しなければいけないとしたら、それはいま言ったような個人の言語のようなものを、どういうふうにコンピュータが包み込んでいくのか、そもそもコンピュータはそれで動く機械なのかという、根源的なところに行く問題だと思うんですよ。
ある意味ではコンピュータのエラーというのが、実はコンピュータの創造性の鍵ですね。いろんなエラーに対応してくれるコンピュータというのは、創造的なコンピュータかもしれない。ということは、いろんなエラーを起こすマックは創造的なコンピュータか(笑)。
そういう意味ではパロールというのはエラーなんですよ。エラーの中に創造性がある、エラーの中に個性がある。そういう考え方がおそらく出てくるのも、相対性が重んじられるからでしょう。つまり相対性というのは、中心がなくて、一人一人が直面するその場での基準ですから。
編集部
−−言語には祖語があるということは、宗教的に単一の原理があるというわけではなくて、構造として普遍化されたものを、現代使われている言葉が含んでいるということですか。神秘化された何か、ゲルマンの精神とか、そういうものではなくて構造…。それこそまさに構造主義ということなんですかね。
平尾
構造というのが、もっと簡単に言っちゃうとパターンとして、「テキスト的」に説明するぼく達の神話や「テキスト的な思想」とはまた別のものとして「構造」が見えてくるというのが、構造主義の考え方だと思うんです。ヨーロッパだと「テキスト的な枠組み」としてユダヤ・キリスト教の思想がありますね。そうじゃないところに構造が出せるということじゃないですかね。そういう意味でいうと、ポストモダンの思想の走りとして構造主義が出てくるわけでしょ。それはなぜかというと、いままでの哲学史に呪縛されていないような新しい考え方。それを出せる「可能性」として期待した人が多いんだと思うんです。ただ、構造主義が現実にそうなり得たかどうかについては、人によって評価が違うところだと思います。
例えば「テキストの解釈」というポスト・モダン的な考え方があります。そういう考え方をすると、「神話」を見ると、その中に様々な構造が隠されているわけでしょう。そして「言語」の中にも構造が隠されている。ということは、「小説」の中にも構造が隠されているわけだ。というふうに見ていくと、「テキスト」というのはテキストの「言葉の意味を読んで考える」こと以外の扱い方があるということですよね。マルクスを小説として読んでもいいし、あるいは夏目漱石を経済学として読んでもいいわけです。こういう自由さがあるわけです。構造的なとらえ方ではね。
ただ大事なことは、そこでぶっ飛んじゃうものは、意味ですね。そういうことをやって「何の意味があるのか」といった時に、やはりポストモダンの行き着く先は、「意味があると思うからいけないんだ」という、いわゆるデ・コンストラクション(deconstruction・脱構築)になっていくわけです。最初から意味なんてないんだと。
でも、こうした議論は「それを言っちゃおしまいだ」っていう結論になっちゃいますね。それを言っちゃうと、もう何を言っても無意味になってしまう。どうも最近の若い人達がすぐに柄谷行人に飛びついたりするような傾向は、それが根底にあるのではないでしょうか。本当は、柄谷に行く前に色々と学ぶべき大切なものがあるのに、いきなり柄谷から出発しちゃまずいんですよ。柄谷から昔にさかのぼっていくんだったらいいけどね。
編集部
−−最近、固有名の問題とか言われていますよね。それは、やはりそこから無意味の意味を見いだすみたいなことがはやってるのかな。
平尾
固有名の問題って、具体的にいうと?
編集部
−−相対的な、それ以外の外の価値基準で計り得ないような、意味のなさが意味があるという…。
平尾
哲学で「固有名の問題」というと、「名前とは何か」という問題なんですよね。名前には意味があるのかという。名前には意味はない、ただの符号だという一つの立場がある。名前というのは文化的なものだという立場もある。それは子供に聖人の名前を付けるような例ですね。もう一つラッセルが言っているおもしろいアイディアは、名前はラベルだというんです。どんなラベルかというと、名前というのは一種の「説明書」なんです。ぼくは「ヒラオハジメ」だ。「ヒラオハジメ」というラベル(インデックス)にしたがって中身を調べて見ると、「男」とか「髭を生やしてる」とか「武蔵美で教えてる」とか、いろんな「説明」がくっついている。その「説明」をずっと長く、落語の「寿限無」みたいにくっつけて名付けてもいいんです。ヒラオハジメというのはこれこれこういうやつで…と。でも、それはめんどくさいから「インデックス」として、ビデオにラベルを貼るように名前を使う。
ということは、すべての固有名は「ラベル」であるというふうに言っちゃうと、これは大変なことになりますね。つまりぼく達は世の中のあらゆるものを名付けていますけれども、名付けというのはインデックスで、実はその背後には説明がある。これは人工知能にも使われているアイディアで、名前がラベルだとすれば、それにどういう説明をつけるかは最初に定義しておけばいい。これは、推論ができるコンピュータ言語のLISPやPrologで使われています。それらの言語には「集合の定義」があって、例えば、親と子供はこういう関係である、だからジョンはトムの親である、さらに、ジョンというのはトムの父親か母親のどちらかであるという定義がそのバックにあるわけです。「親」と言った瞬間に、それがコンピュータの中ではインデックスとして扱われるわけです。
そういうふうに考えると、「意味」というもののとらえ方が変わってきますね。意味が「解釈」ではなくて、「集合」になっていくわけです。数学者とか論理学者とか、コンピュータを設計する人は、たぶん「意味」についてはそういうふうに考えている人が主流だと思うんです。コンピュータが「意味がわかった」というのは、あるインデックスに対して、それがどんな集合かを知っていて、メモリーの中にそれを持っているということなんですね。
おもしろいのは、そこで翻って言うと、「では人間はコンピュータと違うのか」ということですね。人間もそうじゃないかと、ラッセルは提案するわけです。そうすると、ぼく達も名前のバックにさまざまなそういう集合を持っていて、その意味の集合の中で過ごしているのにすぎないのではないか。
ソシュールが最初に言語というものを、それまで「神からもらったもの」であったのをもっと即物的に扱うようにしましたよね。それがきっかけになって、いろんなところで言語をどういうものとして扱うかということが自由になって、今、コンピュータが近づいているのはそういうアイディアでしょうね。これも相対化ですね。
寺山
それももうちょっといろいろ突っ込んでいくとおもしろいなと思うんだけれども、構造主義が出てから社会的な影響としては、レヴィ・ストロースなんかの影響が大きいと思うんですけれども、ヨーロッパ中心的な社会、近代モダニズムというのはヨーロッパ中心で、さっきから出てきている話は基本的にヨーロッパの視点から立った歴史ですね。それに対しての初めて大きな衝撃というか、揺さぶりは、第一次世界大戦後のヨーロッパにレヴィ・ストロースの構造主義が姿を現した(ということです)。 現実的には第一次世界大戦でヨーロッパが戦場になって、戦車が現れて、毒ガスが使われてという、ある種の近代の危機を現実的な部分で非常に感じていた部分がある。それにたたみかけるように、ちょうど重なっていくようにレヴィ・ストロースなんかが語った、見えないものが見えるようになったというのは、彼が調査した非ヨーロッパ的な、反合理主義的・前近代的な場所というものが、ある意味で自分達が考えているよりはるかに高度なシステムを持っていたという発見がありますね。
そのことが一種、近代的な自分達が考えていた、直線的に言えば自分達が先頭にいると考えていたものに、非常に疑いをもたらした。これもアインシュタインの相対性理論と同じように、明快にビジョン化されているわけじゃないんだけれども、ちょっと違うんじゃないかと。これもさっき話に出てきてますけども、東洋と西洋みたいな、単純に二元論ではないんだけれども、西洋の生き方に対するある種の非西洋、東洋と言ってもいいんですが、ライプニッツの考え方がイメージ的にいうと曼陀羅に近いというような、クロスするような土壌がだんだん出てくる。
そういうことと重なりがあるのかなということが一つと、それからちょっと乱暴かもしれないんですけど、もう一つはちょうど同時代的に原子爆弾ができるわけだけれども、原子とか分子とかといったミクロな科学的な探究が片方である。これはヨーロッパの科学主義が言っていくわけで、さっきの話に乱暴に結びつけると、自動車とかはエネルギーの作り方とすればものすごく無駄が多いわけですね。だけど非常にわかりやすい。ある部分に空気を暖めていくと膨張して、その圧縮の力でエネルギーが起こるみたいな話はわかりやすい。
だけど原子爆弾は、ぼくは構造はよくわかりませんけれども、本来たったこれだけの大きさのものがこれだけのものを破壊するようなエネルギーを出すということ自体、さっきの話じゃないけどイメージしにくいわけですよね。従来の、17世紀や18世紀のようなイメージでエネルギーの問題を考えていたのでは、とうてい原子爆弾みたいなものはイメージできない。だけど、同時にそういうことは考えられていたと思うんです。
たぶん原子とか分子という新しいイメージがなければ、それは作られない、不可能だと思う。原子というのは、原子爆弾とか非常に破壊的なイメージが強いので、ぼくもあんまり考えたことがなかったんですけれども、実際ああいうものが生まれてるということは、エネルギー変換のメカニズム・全然違うメカニズム(の発想)が同時平行的に二〇世紀には起こっていた。そこらへん、このあいだ紹介していただいた「複雑系」といったものの歴史をたどっていきますと、分子生物学ですか、そういうもののイメージのとらえ方がずいぶん変わってきているという流れが一つあると思う。
その流れの中に多分に東洋的なと言ってもいいような関係性、エネルギーが直接ぶつかって何かやるというのではなくて、もっと有機的な絡み合いというか、うまく言葉で説明できるメタファがないんですけれども、そういうふうな流れがその中に平行して起こっているのかなというイメージがちょこっとあるんですけどね。
平尾
ただ、それはちょこっとなんですよ(笑)。ノーベル賞をとった人でいうと、イリヤ・プリゴジンという人がいますね。プリゴジンはやはり東洋の思想も知っていて、有機体論的なオーガニズムの哲学、有機体論的な世界のとらえ方をしようとしています。そもそも宇宙、この世界というのはもともと非平衡的である。つまり簡単にいうと、我々は物理現象を考えるのに方程式で答えを出しますが、今の状態から1秒前にはこうだったはずだというふうには言えないものである。計算していくと次の状態は出てくるけれども、多くの要素がもう変化してしまっているので、前の状態には戻れない。自然は非平衡的であって、そして常に運動していて、しかも非線型、すなわちカオス的なものですね。計算はできるけれども予測はつかないようなものであるというわけです。
プリゴジンは、私がたまたま研究しているホワイトヘッドという哲学者の影響を強く受けた人なんですね。昔、大学院生レベルの人達のシンポジウムがあって、やはり若い人達が集まるといろいろ新しいアイディアが出るんですけど、そこで有機体論を研究している人が私ともう一人、いま岡山の大学で教えている人がいて、二人が提題者になって発表したんです。
その時にいま言ったようなアイディア、「有機体論的な哲学」というのがこれからどんどん科学の中に取り入れられていくべきだし、重要なんじゃないかと発表したら、質問者がいて、「そう言うけれども、現実にそんなこと言ってる科学者は一人もいないじゃないか」と。その時にもう一人の科学史をやっている人が、具体的に何人かの名前を挙げてくれたんですけど、でも実際、多くはないです。たとえばシステム論の元祖のベルタランフィという生物学者、そしてプリゴジン、そのほかオーストラリアの生物学者など、何人かしか挙げられないぐらい、影響力が少ないのも事実です。
ただ、今後そういう影響が広がっていく、いままでの西洋の枠組み的ではない考え方が広がっていく可能性はあります。可能性はありますけど、そこで非常に強固な壁になっているのは、やはり近代合理主義の壁ですね。自然の事物は絶対「メカニズム(機械論)で説明できる」と言う人が圧倒的多数です。科学者、特に医学者や生物学者ね。彼らはものすごくそれにこだわってますね。
それはなぜかというと、やはり、ある意味では、そうした学問は(日本では)数学から遠いからかもしれません。少しでも数学に詳しい人は、非線型の数学の世界を知っているので、非線型のモデルが生物にはあると思ってるみたいなんですね。あとエコロジーをやってる人ですね。エコロジーを研究している人は、動物の個体数などを大局的な視点で見ているので。
結局、分子生物学などを考えてみると、それまで化学の人がやっていたこと、あるいは原子物理学の人がやっていたことを、ようやく今、生物の体の中の問題として考えているわけですね。その分野では一番新しいのだけれども、原子や分子のふるまいから考える発想は、もう昔からあるアイディアですね。だから、それが一つの学問の中でまとまってるというところに、たぶん古さが残ってるんだと思うんですよ。
いままでよくわからなかった生物の仕組みが、分子や原子を考慮に入れたとたんにわかるようになった。いままだその段階ですね。だから、原因と結果の非常に単純な因果関係の理論の中で分子生物学もまた研究されているし、何と言ってもその典型はDNAの発見ですね。DNAというのが、いってみれば「究極原因」なんですね。もうすべてDNAだと。だから、その中で先走った人なんかは「DNAさえ研究すれば文化のことも全部わかるんだ」と、(利根川進なんか言ってますけど)そういう人もいます。
ただ、それは結局、「原子を研究すると物質のふるまいが全部わかる」と言ったのと同じで、実際はそうじゃないわけですよ。たとえば水素原子のことを一生懸命研究しても、「結びつき方」が問題なので、(結びつき方でこれだけの原子のバリエーションができるわけで、)結びつき方を研究しなければ、原子自体を研究しても、それ以上のことはわからない。
寺山
「原子を研究すればすべてがわかる」というのはすごく古い、従来の合理主義的な発想ですよね。
平尾
分析主義ですよね。最小の要素を研究すれば、何でもわかると。(でも例えばネジを研究しても、ネジのことしかわからないんだけど…。)そういう考え方がありますね。
原子爆弾について言うと、直観とスケール感という問題としていま考えていることがあるんですけど、それはぼく達の「直観」がありますね、空間や時間の。やはりそういうものが時代を追って変わってきてると思うんです。それとともに「スケールについての感覚」が変化してると思うんです。どういうことかというと、原始時代にはわれわれの持っている表現の手段というのはまだ文字がなくて、絵画だけなんですね。そうすると絵画的な直観、空間の直観に従ったスケール感がそこにはあって、それはたとえば「神も目に見えるものである」というスケール感です。つまり絵を描くということしかないから、「神」も「目に見えるもの」になっちゃうし、すべての自然現象は「目に見えるもので説明できる」わけですよ。
そうすると確かに宇宙というものを説明はできるんだけど、「宇宙の形」自体はとても小さな(日常的な)ものでしか説明できない。「太陽が船に乗って空を航行する」というような。ところが言葉というものが出てきて、文字が出てくると、スケール感がやはり広がっていく。どういうふうに広がるかというと、「描けないものを語る」ようになるでしょ。そして「すごく尊いものは実は絵には描けない」ということになってくる。原始時代は尊いものはみんな描いていたわけですよ。
しかし、文字文化が出てくると、ユダヤ教でもイスラム教でもそうだけど、偶像にできるようなものはまだレベルが低いのであって、「偶像にできないものが尊い」というようになってくる。そうするとこのスケール感というものがもっと広がっていきますね。どういうふうに広がるかというと、それは「内面的な広がり」だと思うんですけど、「ぼく達の心や想像力の広がりの大きさ」になっていく。ぼく達が「ぞくぞくする感じ」とか、あるいは「不安な感じ」とか、そう感じるものが直接言語の中に反映してきて、独特の「宗教的な神秘」というスケール感になっていく。
それが今度は近代になっていくと、文字の中に数学という表現が出てきますよね。そうすると、今度はわれわれの直観と数学的な表現というものが影響を与え合って、数学的直観も出てくるわけです。「数学的直観」というのは、それまで言葉で説明していた「直観」を、かなり整然とした形でまとめたものなんです。その結果、今、われわれは「ずいぶん遠いところにあるな」と思うかわりに、「何キロぐらい離れてるんだろう」と思ったり、それこそルノワールの絵を見て、「ああ、きれい」と言うかわりに、「いくらぐらいかな」と思ったりとかね。いろんな数学的直観に基づいて生活しているわけです。
それと同時に映画が作られてくると、動画という「動きの面での新しいスケール感」も出てきますね。現代というのはそういう意味でいうと、マルチメディアのスケール感がある時代だと思うんですよ。「マルチメディアのスケール感」というのは、やはり視点を移動するとどうなるかとか、あるいは、今、ここは昼だけど地球の裏側は夜だとか。さっきの相対論的な感じ方に似てきますね。
そうやってわれわれの直観というのは、生理学的に言えば昔の人もいまの人も同じはずなんだけど、どうも違うらしいんですね。昔の人にとっては山はもっと近くに見えていたし、それこそ空ももっと近い。「星に手が届く」と思っていたわけですから。そういう意味でいうと、ぼく達がさまざまな観測手段とか数式などの表現方法を知ることによって、だんだん「スケール」というものが大きくなっていったんじゃないかという気がするんですよ。
原子というのもまさにその一つの証拠なので、ライプニッツの時代にもうすでに原子論自体はあった。ただライプニッツの時代の原子というのは三角錘だとか、いや立方体だとか、きわめて単純な形で思い浮かべられていて、しかも原子と原子がつながるのはおそらく鍵があって、フックで引っかかっているんだろうと発想した。これはなぜかというと、当時やはり機械論が主流だったからですね。そして当時の技術では、「機械技術」が一番新しいんですよ。だからライプニッツ自身も、もしも将来われわれが人間と同じものを作れるとしたら、その内部にはテコとか歯車とかさまざまなものが組み合わさっているだろうと言ってますけれども、そういう目で生き物を見ていた。
ところがだんだん観測技術が上がってくると、われわれの顕微鏡で見えるものよりもっと小さいものがどうもあるらしいとわかる。原子というものに関して決定的だったのは、観測問題というやつがそこで生まれて、つまり原子というのは「目で見ることもできないし、見ようとすれば形が変わってしまう」ものである。これはハイゼンベルグの不確定性原理ですね。すなわち位置を調べようとして、原子を止めると速度、運動量はわからないし、そしてまた運動量を調べようとして原子を何かにパーンと当てると、運動量はわかるんだけれども、動いちゃうから位置は観測できない。
それは観測技術の問題じゃないかとアインシュタインも思っていたんですね。アインシュタインは最初、位置と運動量は同時に決定できると思っていたんだけれども、根本的にそれは不可能だということをハイゼンベルグが証明した。原子というのは非常に妙なもので、それまでのわれわれのいかなる直観でもとらえられない。位置をとらえれば運動量はわからないし、運動をとらえれば位置がわからないような、そういうものである。そういうものとして見るしかない。
さらに言えば、原子は目に見えない。というのは、目で見るためには光を当てなきゃいけないんだけれども、原子に光を当てると動いちゃう。強い光を当てれば当てるほど動いて、もう見えない。いったいどうやってこれをとらえるか。動かないようにしようと思えば、光よりも短い波長の電磁波、ガンマ線とかを当てなきゃいけない。しかし、波長の短い光はエネルギーが大きくて、そういうものほど原子を変化させてしまうんですね。だから、根本的に確率で原子を考えるしかない。有名な「コペンハーゲン解釈」というやつです。
そういう意味でいうと、原子というのはぼく達の知っているようなもののふるまいをしないということ。原子というのはひどくわれわれの直観から切り離されているということ。そこにやはり、さっきの、「なぜ原子爆弾があんなに強力なのか」という、われわれの根源的な原子爆弾に対する「恐れの感覚」が出てくるように、ぼくは思うんです。
原子爆弾というのは、もうぼく達の直観でとらえられるものじゃないわけです。原子爆弾のエネルギーとその原理を説明すること自体がね。だから20世紀にもしも革命的なことが一つ、ぼく達のものの感受性の上で起こったとすれば、たぶんそういう問題でしょうね。「見えない構造を見えるようにする」という構造主義も、そこまでは行ってなかったと思いますね。原子爆弾の持っているわかりにくさというのは、その点で大変なものだと思います。
ただ一般の人はやはり、説明してもそれはわからないと思うんです。それはぼく達自身が、「物質はエネルギーに変わる」と言われたってわかんないですよ、直観ではね。ただ、現実に広島でも長崎でもそれが起こった。それでまだまだ問題なのは、広島・長崎で起こったことは、物質がエネルギーに変わることのほんのわずかな部分の現実化でしかないということです。
つまりあの時起こったことは核分裂ですけれども、核分裂というのは実際に物質がエネルギーに変わる時の何万分の一か、何百万分の一しかエネルギーを使ってないんですね。だから、ほんとうにそれを効率よく使おうとすれば、一つ上のレベルの核融合やもっと上の、反物質と物質の反応を待たなければいけないんだけど。
現代の物理学では、核物理学が出てきた時にわれわれの直観を超えなければいけなかったんですね。そうすると論理学でも、量子論理という特殊な論理が出てきて、この「量子論理」というのは確率論的論理なんですね。まだ量子論理というのは論理学として発展途上のものなんです。例えば、電子がある場所にあるかないかの確率は50%であるというような問題が出てきます。今まで「存在」について論理学で語る時に、ここにペンがあるというのを記号で表現することはできたんです。しかしここに原子があるかないかは50%の確率であるというのを、「存在」の記号で表現していいか。「存在」としてそれを語っていいか。根本的に量子の世界、原子の世界の論理というのは、これまでの論理からすればそういう疑わしい面をもっているのです。だから、いま論理学の世界で最も物理学のほうに近いところをやるとしたら、その量子論理はトピックだと思うんですけど、これは難解なものなんです。竹内外史さんという数学者がそれをアメリカでやってますけどね。
そこまで行っちゃうと、やはり原子爆弾というのはわけのわからないものであって、わけのわからないものだからこそ、「信仰」もそこに出てくるわけです。アメリカとソ連の戦後の軍拡競争、あれは何だったのかというと、ある意味ではわけのわからない「お原子様」に対する信仰であるというふうにも言えると思うんですね。それこそ核爆弾なんて10発ぐらいあれば、もうそれだけで脅しとしては十分なんですけど、それを3万発とか4万発とか作ってしまう。そのばかばかしさね。そんなものたとえ作ったって、使い道ないわけでしょ。これはもはや信仰ですよ。
実際に最近、アメリカの元政府高官なんかがいろんなところで語っているのを読んだり聞いたりすると、やはりそれは信仰ですね。「核に対する信仰」と、もう一つの信仰は「共産主義に対する恐れ」というのがあって、これはほとんどキリスト教の信仰と異教徒に対する恐れと変わらないです。共産主義は怖いからアトミックボム様を拝み倒す。
寺山
むりやりいままでの話をまとめますと、20世紀的なものというのは、一つではないのかもしれないけどあって、それはトータルに言えば「見えないものを見るため」(ということで)、ハイゼンベルグといった人達の考え方もそうだ。だけど従来のやり方では見えないのだから、四次元の立方体もそうですけど、そこらへんは通底していて非常におもしろいなと思うんです。
ちょっと確認なんですけど、プリゴジンとか出ましたね、それからベルタランフィ、この人達は二〇世紀に入ってから(の人?)。平尾
プリゴジンはいまも健在の人で、ベルタランフィは戦前に活躍した人です。生まれは19世紀ですね。
to be continued