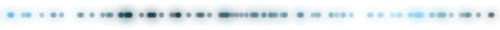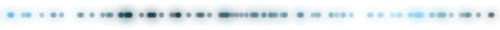


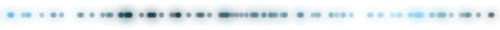
1990年代を特徴づける最大の社会的事件は何か、と問われたならば、「オウム真理教による地下鉄サリン事件」と答える人が多いだろう。それほど、私たち同時代人にとって、あの事件は衝撃的であった。ただし、衝撃的であったのはオウムが「想像もできない事件」を起こしたからではない。誰もが「空想はするが、まさか実行しようとは思わない」事件を起こしたからである。思春期には、誰だって親と喧嘩して「殺してやりたい」ほど悔しく思うものだ。定期試験ができそうもない時には「学校が燃えちゃえばいいのに」と思うし、盛り場で不良にからまれた時には「機関銃があれば皆殺しだぞ」と心の中で啖呵を切る。それらは人間として当り前の心理である。しかし、人間には、何らかの原因で心の中の空想を抑えられなくなることがある。すると、それは「妄想」となって人間を襲い、犯罪行為を実行させ、本人とその周囲の人間を破滅に導く。そういう場合でも、多くの「犯罪者」は「魔が差した」と感じ、後悔する。
オウムが人々を驚かせたのは、こうした「空想の壁」をやすやすと乗り越えて毒ガスを作り、軍用ヘリを買い、機関銃の量産を計画し、気に入らない人間を抹殺したからである。その思い切りの良さと実行力は、キューバ危機やベトナム戦争への介入、宇宙開発とセックス・スキャンダルで六〇年代前半を走り抜けたケネディ大統領のそれを思わせる。(カッコよさの点は措くとして。)
評論家も普通の主婦も、人々の疑問は同じである。「なぜ、高学歴の信徒があんなに大それた犯罪行為を行なったのか。」答えのヒントは、裁判やインタビューで若い出家信徒のほとんどが語る「尊師はどんな疑問にもたちどころに答えてくれる。すごいと思った。」という言葉の中にある。
人生に疑問はつきものである。しかも、「宇宙の神秘」から「明日の自分」に至るまで、「わからない」ものほど大きな価値をもっている。そうした「わからない」ものを軽く解き明かしてしまう「指導者」に出会ったら、深く悩んでいる者ほど強く惹きつけられることは想像に難くない。
しかし、よく考えると妙である。頭脳明晰な者がなぜ難問を自分の力で考えないのか。なぜ、自分に関して深く悩んでいる問題の解決法をたやすく他人に尋ね、安直な即答に満足しているのか。なぜ、まだ若く人生経験も少ないのに「解脱」できてしまうのか。要するに、学歴の高低などに関係なく、「どんな難問でも必ず答えが見つかる。」「自分で考えてもわからなければ、人に聞けばよい。」と考えているところが最大の問題なのだ。
私の専門は哲学だが、思想史を眺めると必ず繰り返し登場する難問がある。「宇宙の大きな秩序と人間の行動規範はつながっているのか」「人間は何ものにも制約されず自由に生きられるか」「人間も含め、全ての存在に意味はあるのか」などの問いは、古代から現代まで、宗教から最新の科学的な哲学に至るまでの知によって、ありとあらゆる時代と場所で問われてきたのである。時折、自称「思想家」が「私はこんなすごいことを思いついたぞ!」と叫ぶことがあるが、よく聞いてみると、その「新発見」は仏教の教義に入っていたり、17世紀の大哲学者の説を焼き直しただけであったりする。自称「思想家」氏は単に不勉強で、先人の教えを知らなかっただけなのだ。このこと自体が「難問」への取り組みがいかに困難かを教えてくれる。
難問には近づくための道のりが必要だ。それゆえ、難問は豊かでありうる。さて、われわれは、もうお手軽に、簡単に考えるのをやめようではないか。難問にぶつかった時には、自分の力で悩もうではないか。そして、悩むことの意味自体を重んじ、悩みながら生きていく強靭な精神を鍛えようではないか。「知に携わる者の使命は難問の擁護・難問への敬意である」と、荒涼たる世紀の終わりに立ち、私は敢えて宣言する。